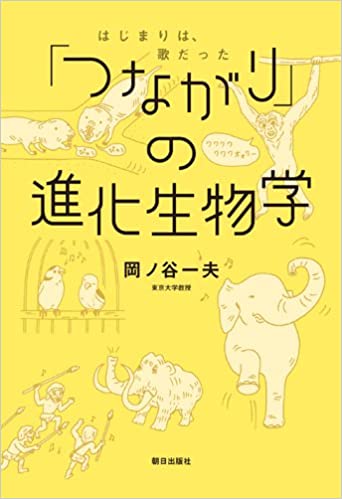予防運動研究会では予防に関わる際の必須の知識として、進化や生物学を学ぶことを推奨しています。
第4弾では、コミュニケーションや、心と体の「正常」とは何か?を生物学の視点から紐といていく、研究会代表おすすめ書籍《つながりの進化生物学》について、代表 中村尚人にインタビューしました。
今回ご紹介するつながりの進化生物学では、コミュニケーションを生物学の視点から、特に鳥のさえずりから紐解いていきます。
僕たちが「心」って言っているものは一体なんだろうか?言葉の起源とはなんだろうか?というすごく示唆にとんだ内容です。
動物も鳴き声でコミュニケーションをとったりはしていますよね。 だけど、人間は『言葉』を使って表現し、伝えあっています。 ただの音のつながりである言葉を、なぜ僕たちは概念として理解できるのか。 なぜヒトの子どもは、特別習うわけではないのに「ママ、水とって」と自然に言えるようになるのか。その答えは、実は歌にあった、という話です。
ただの音のつながりである言葉を、なぜ僕たちは概念として理解できるのか
鳥の鳴き声は「ちゅんちゅん、ちゅんちゅん」「ちゅんちゅ、ちゅんちゅ、ちゅちゅちゅちゅ」とか、ちょっとずつ違いますよね。「ちゅちゅちゅ」と「ちゅんちゅん」は、それぞれ違う意味を表しています。
例えば敵がきたことを知らせるとき「きききき」と鳴きますが、求愛のときは「きゅうんきゅうん」と鳴きます。音が異なると意味が異なるんですね。その音が長くなったものが歌なのです。 色々な音がある中で、この音はこの意味、というように分けることができるようになった、というのが言葉の起源だということです。
なぜヒトの子どもは、特別習うわけではないのに「ママ、水とって」と
自然に言えるようになるのか
僕たちが赤ちゃんに「○○ちゃんかわいいわね〜」と話しかけても、はじめは単なる音としてしか赤ちゃんには聞こえていません。
しかし繰り返し名前を呼ばれていると、「○○ちゃん」という音がいつもついているな、「○○ちゃん」は私のことなんだ、と認識します。そのときに、「○○ちゃん」という『言葉』になるんです。
同じように、やってはだめなことをしたときに「だめよ」と言われることが何度もあると、「だめよ」というのは禁止を指す音なんだ、と理解します。
音が繰り返され、言葉になってくるんですね。
人間は色々な言葉を発することができます。50種類くらい発音ができるのですが、その発音の組み合わせで言葉を作っていきます。だから、何百通り何千通りと組み合わせができて、たくさんの言葉ができるんですね。 こうやって言葉というものの起源を紐解いていくと、言葉はもともとは音、歌で、そこからヒトは言葉を得てきたということがわかります。
手紙になり、電話になり、今はメールになり、他のコミュニケーションがどんどん削ぎ落とされてきている
そして、言葉は心を表すようになってきます。この本では、心とはなんだろうか、ということも、すごく科学しているんです。
僕たちは心を言葉で表現していますよね。言葉をこころの比喩として使っています。
僕たちの言葉がすごく複雑になったのは、伝達手段として使用できるよう独立していったためです。僕たちは考え事をしたり、独り言もいいます。書籍になったりもできる。言葉が独り歩きをするようになりました。
だけど、本当は言葉だけではなくて、表情やボディランゲージ、抑揚や口調、そういったもので僕たちは本来コミュニケーションをして、伝えあっているんですよね。
触れるとか、ハグをするとか、そういったものが本来のコミュニケーションなんですが、今は言葉だけが独り歩きをしてしまって、言葉だけで理解できるようになってきている。
言葉が手紙になり、電話になり、今はメールになり、他のコミュニケーションがどんどん削ぎ落とされてきているんです。『言葉第一主義』のような、言葉さえあれば伝わる、というように。
でも今、色んな歪みがでているのはそういう背景もあるのではないか、ということです。
言葉よりも、無意識に本音が出てしまう表情とか目だとか抑揚なんかが正直な信号
僕たちは何かを伝えるとき、信号を使っています。信号には正直な信号とそうではない信号というのがあります。 言葉で「好きだよ」という音の信号を使っていても、「別に好きじゃないよ」という顔をしているとしたら、正直な信号はどちらでしょうか?表情の方が正直な信号ですよね。
ひとはほら、口で色んなこと言っても目で嘘はいえないってところがありますよね。
実は言葉よりも顔面筋・表情筋の方が正直な信号です。
あとは抑揚。震える声で「大丈夫ですー」と言っていても、大丈夫じゃないですよね。
信号は正直じゃないと意味をなさなくなります。
だから実は言葉よりも、無意識に本音が出てしまう表情とか目だとか抑揚なんかが正直な信号としては価値があって、本当はそういった視点で人を見て、コミュニケーションをとらないといけないんだよという話です。
この本には色んな話が書いてあって、とても面白い、とにかく面白いんです!
ヒトとはなにか?心とはなにか?コミュニケーションとはなにか?
そうやって考えていくと、ストレスはなにか?とか、色々なヒントが入っているんです。
親子関係の中での、接触する、ハグする、タッチングの大事さ
あと、ヒトならでは、という話が色々でてきます。
子どもを抱っこするのは霊長類であるニホンザル、チンパンジー、ヒトしかないんです。
動物は子どもを抱っこするというのはないんですね。
そういったことを知った上でみていくと、親子関係の中での、接触する、ハグする、タッチングの大事さというのがすごく見えてきますよね。
あと発声学習も、ヒトならではです。
僕たちは言葉を何度も繰り返して、子どもに言葉を教えていきますが、こうやって子どもが発声や言葉を習うことができるのは鳥とヒトだけなんです。他の動物はできないんですよ。
そういう意味では、鳥もコミュニケーションという点においてはすごいですよね。
そういったヒトならではという話、ヒトとしてのヒントが山ほどでてくるので、面白いですよ。読んでもらうと視野が広がってくると思います。
喜怒哀楽のようなもの、情動というのは多くの動物にある
情動と感情とは違うというお話もあります。
情動は基本的に快・不快で表され、感情の方がより複雑です。
不快で遠ざかろうと思ったら恐怖です。恐怖は逃げる、逃避するんですよね。
快で近づくのは愛、喜びですよね。
私たちは快なものには近づくし、不快なものからは遠ざかります。
でも、不快なんだけど近づくことがあります。
怒っているときは「このやろー!」って向かっていくでしょう。怒りというのは嫌いだけど近づく。
このように、喜怒哀楽のようなもの、情動というのは多くの動物にあるんだということです。
動物でも、怒りだったり恐怖が倍増すると攻撃的になりますし、怖ければ逃げるし、良ければ近づいてくるし…
でも感情という妬みだとか恨みだとかは、記憶なんかも入ってきますから、人間関係のように関係性がない成り立たないわけです。
「誰々が○○したから憎たらしい」というように、快不快だけじゃない、人間のいわゆる複雑な感情になってきます。
心というものも、生物学的に捉えるととても面白いなとおもいます。
ハンス・セリエのストレス説もそうですが、例えばクライアントに何か不調があって、交感神経を高めている、という事実があったときに、心というものを生物学的に捉えていれば、その現象が人間だけに特有のものなのか?それとももっと根源的なものなのか?と分かってきますよね。
生物学的に不快と感じているのに、でもそこから遠ざかれない、そこにフラストレーションが起こっているとか…。
この本は、心とか感情を理解するのにすごく役立ちますから、ぜひぜひ読んでみてください。
正常というものをつきつめるのならば、やはり生物学を知っておかないと
生物学的な視点でヒトと相対することで、ヒトというものの捉え方がすごく広がります。そして、なぜ予防でこのような視点が必要かというと、何が正常で何が異常なのか?を知らないといけないからです。正常というものをつきつめるのならば、やはり生物学を知っておかないと。
「生物学的にみて、それはよくないですよね」「母子関係において、接触がないというのは、問題ありますよ」と言える。 例えば、正直な信号としての顔面筋とか表情の大事さとか、言葉だけで翻弄されてはいけないよ、とか、色々な意味で生物学を学ぶことは必要ですね。
ヒトに関わる上でのひとつの指標というか、道筋をつくってくれますので、僕は生物学を勉強するといいと思っています。
あと、科学なんですね。科学的に鳥とか他の動物と比較をしていますよね。例えば発声学習ができるのは鳥とヒトですよ、というように。人間に特有なものをいかに科学的に導き出していくかということは、そこに何かしらの生物としてのヒトの真理があるから。
それは心にしろ身体にしろ、予防に関わる上で、正常はなにか?健康とはなにか?と見ていく。人間として生物学的なものは知っているにこしたことはないかなと思います。